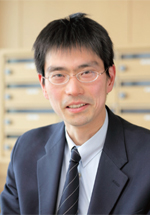
法律学科
教授 富永晃一
みなさんも、「日本企業(日本人)は残業が多いが生産性が低い」といった議論を見聞きしたことがあると思います。もちろん企業も人も多様であり、安易に「日本(人)は・・」などと論じるべきではないのでしょうが、確かに少なからぬ日本企業では相当の長時間残業が行われています。1990年代以降、全労働者平均での年間労働時間数は減少していますが、これはパートタイム労働者など非正規労働者の増加に伴うものであり、正社員の労働時間はあまり減少していないのです。
最近、長時間労働や正社員・非正社員の処遇格差などの弊害が注目され、硬直的な日本企業での働き方を変えようとするいわゆる「働き方改革」の一環として、長時間労働を抑制する試みが国により実施されています。ここでは種々の施策の中でも、特に法律上の時間外労働(残業)への上限規制の改正についてごくごく簡単にご紹介しましょう。
「労働基準法」という法律では、「原則として」労働時間の上限は、1日8時間、1週40時間とされています。法律で認められる例外や特例・適用除外にあたらないのに、この上限(法定労働時間)を超えて残業させることは犯罪となり得ます。
仕事には繁閑もあり、残業が不可避のこともあるので、この上限を超えて残業させることができる例外がいくつか法律上に定められています。そのひとつが、会社が職場の代表者(職場の過半数の労働者をメンバーとしている労働組合、それがない場合には職場の過半数の労働者が選んだ代表者)と残業をさせていい場合や、そのときの上限時間等について「取り決め」(「三六協定」と呼びます)をした場合です(労働基準法36条)。
この場合、残業させても違法でなく犯罪にはなりませんが、残業時間の労働については普通の定時内の労働よりも高いレートでの賃金(「時間外割増賃金」。いわゆる残業代)を払わなければなりません。
この三六協定の例外には以下のような問題も指摘されてきました。
このうち①は法律面というより運用面の課題であり、②⑤も一応は(一部不十分かもしれませんが)法改正で対応したのですが、③④の問題が残っていました。厳しい規制があるように見えても、実は法律上認められる例外によって、簡単に長時間労働できるようになっていたわけです。
なお長時間労働の実態としての蔓延は、必ずしも使用者だけのせいとは言い切れない事情もありました。労働者側にも、昭和末期までは、残業代による収入向上や、自分の成長(出世)、解雇回避等などの理由で、残業を不利益と捉えない傾向もあったと思われます。
長時間労働という仕事面への「極振り」は、反面、何らかの形で家庭面を支えてくれる人(妻、親など)を必要とします。昭和末期くらいまでは、妻が家庭の責任を負い、夫が長時間労働で収入の責任を負う、という家庭像がスタンダード視され、この分業体制を支えてきたのだと思われます。
しかし平成年間を通じ、少子高齢化の進展、単身世帯と共働き世帯の増加、産業構造の変化等により、今では年齢性別既婚未婚等で働き方を限定させてしまうより、意欲や希望に応じた柔軟な働き方を可能にして、多様な人の労働参加を促すべきという考え方が有力化してきています。働き方改革も、こうした時代の変化の表れの一つなのでしょう。
労働時間の上限規制については、働き方改革により上記の③④の問題への対応が図られました。働き方改革の一環としての2018年の法改正により、三六協定に定める時間外労働の上限を、法律で原則として月45時間、年360時間とし、特別条項についても年720時間、単月100時間未満/複数月平均80時間を上限としたのです。
三六協定上の上限時間数(原則)は変わらないのですが、法律にこの上限を書き込んだことで、その上限超過の三六協定は無効となります(③への対応)。また特別条項についても、青天井でなく上限ができました(④への対応。この新しい上限時間数は、過労死ラインを超えないものです)。もっとも、自動車運転業務や医師等、一部の業種・業務については、特殊性を考慮して例外ないし適用除外が設けられています。
法律の、現実を規制する力(「実効性」)には限界があります。法律上の規制に取締りが不十分だったり、現実離れしていたり弊害があったりすることもあります。後者の点についていえば、規制にはプラス面だけでなくマイナス面(副作用)もつきものであり、今回の働き方改革に伴う法改正に対しても、「労働者の成長を阻害する」「日本の競争力を低める」「違法残業が却って増える」といった傾聴すべき批判もあります。(上限規制以外も含めた)種々の施策の長時間労働の削減効果も、まだ未確定の要素が残っています。
もっとも労働時間の上限規制については、理論的には、労働時間の削減効果を有するとされています(山本勲『働き方改革関連法による長時間労働是正の効果』日本労働研究雑誌702号29頁(2019))。監督・取締りを適正に実施することで違法残業への移行を押さえつつ、会社での滞在時間の長さでなく、生産性の高さで成果を稼ぐ働き方に移行することができれば、個人の成長や競争力の維持にも必ずしもマイナスにはならないでしょう。「働き方改革」という社会実験の結果が待たれるところです。